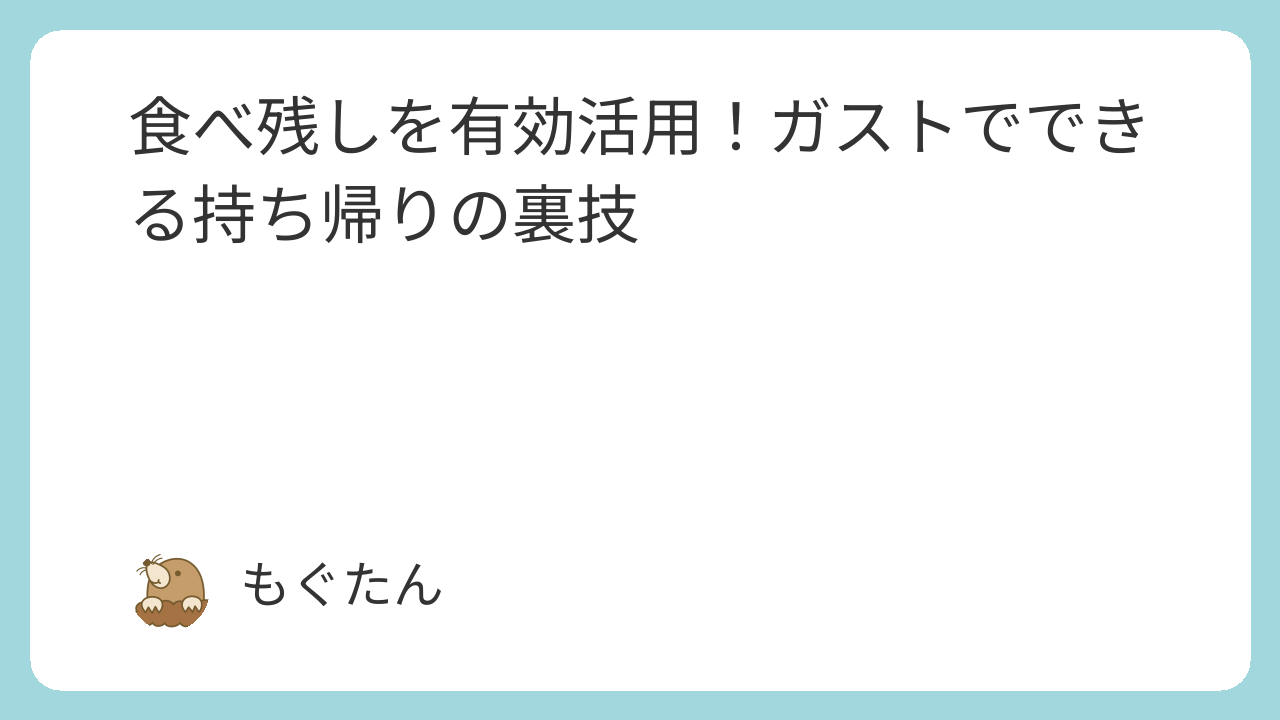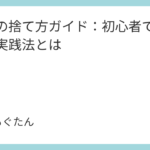家族や友人との夜ご飯、あるいは一人ランチでも使い勝手のよいガスト。
しかし、「頼みすぎて食べきれなかった…」などという経験をしたことはありませんか?
そんなときに覚えておきたいのが、実はガストでは食べ残しを持ち帰りできる場合があるということ!
公式にはあまり知られていないこの**「裏技」**を駆使すれば、無駄になるはずだった料理も家でおいしく食べられるかも?
この記事では、ガストの持ち帰りルールとそのポイントをわかりやすく解説します。
食べ残しを有効活用する理由
食べ残しによる食品ロスの現状
日本では年間約600万トンもの食品ロスが発生しており、これは東京ドーム約5杯分にも相当する膨大な量です。
そのうち家庭や飲食店での食べ残しが大きな割合を占めており、特に外食産業では1回の食事で多くの食品が無駄になっている現状があります。
食材の生産には水やエネルギーなど多くの資源が使われており、それらが無駄になることは地球環境にも深刻な影響を及ぼします。
食べ残しを減らすことは、持続可能な社会を目指すための大きな一歩となります。
家庭での持ち帰り文化の重要性
欧米諸国では当たり前となっている「ドギーバッグ」の文化は、日本では衛生面の懸念やマナー意識の違いなどから、なかなか定着してきませんでした。
しかし近年、環境意識の高まりやSDGsの推進により、日本国内でも少しずつ持ち帰りの重要性が見直されています。
家庭での小さな行動が、社会全体の意識変革につながります。
外食での持ち帰りを積極的に実践することで、子どもたちへの食育や環境教育にもつながるのです。
ガストでの持ち帰りメリットとデメリット
【メリット】
- 食べ残しを無駄にせず、自宅で再度楽しめる
- 家族とシェアして食べることで満足感がアップ
- 食費の節約につながり、経済的にもお得
- 食材や調理の手間が省けるため、時短にもなる
【デメリット】
- 店舗によっては対応に差があり、持ち帰り不可の場合も
- 容器が有料で、コストがかかる場合がある
- 夏場などは衛生管理が難しく、食中毒リスクが高まる可能性も
- 再加熱が難しい料理の場合は、風味や食感が損なわれることも
ガストでの持ち帰り容器の種類
もったいないパックとは?
ガストでは、食べ残しを持ち帰りたいお客様向けに**「もったいないパック」**という無料容器を提供しています。
これは環境配慮の一環であり、食べ残しをそのまま廃棄せず、再利用を促進する目的で設けられました。
もったいないパックは簡易的な作りですが、しっかりと密閉できるため、持ち運びにも適しています。
使用時には自己責任であることを了承する必要があり、店員に申し出るとスムーズに受け取ることができます。
有料持ち帰り容器の位置づけ
ガストでは、料理の種類やお客様のニーズに応じて、有料の持ち帰り容器も用意しています。
特にスープやカレー、煮込み料理など汁気の多いメニューには、しっかりとしたフタ付きの容器が必要です。
こうした容器は、漏れを防ぐだけでなく、レンジ加熱にも対応している場合が多く、自宅での保存や再加熱が非常に便利です。
有料ではありますが、その分安全性や使い勝手が高く、エコの観点からも再利用できるケースもあります。
タブレット注文時の持ち帰り選択肢
近年ガストでは、注文の多くを各テーブルに設置されたタブレット端末から行うスタイルが主流となっています。
この端末では、メニュー選択の際に**「持ち帰り容器希望」**のオプションが表示されることがあります。
メニューによっては表示されない場合もあるため、注意が必要です。
タブレットからの選択が難しい場合や、表示がない場合は、スタッフに声をかけて直接申し出ることで対応してもらえます。
特に初めて利用する場合は、遠慮せず質問することがスムーズな対応につながります。
持ち帰りの具体的手順
持ち帰り容器の注文方法
- 食事中または食後にスタッフを呼び、「食べ残しを持ち帰りたい」旨を伝えます。
- **無料の「もったいないパック」**か、有料のしっかりした容器のどちらかを選びます。
- 容器が提供されたら、食べ残しを自分で丁寧に詰めます。 ※衛生上の理由から、スタッフによる詰め替えは行っていません。
- 忘れずに容器を持ち帰り、なるべく早く冷蔵保存・再加熱を行いましょう。
注文時や会計時に持ち帰りの意思を伝えることで、店舗側も対応しやすくなります。
また、容器の準備や袋詰めに時間がかかる場合もあるので、早めの声かけが肝心です。
食べ残しを持ち帰る際の注意点
- 気温が高い時期は、なるべく短時間で持ち帰り、すぐに冷蔵庫へ入れる
- 再加熱は、電子レンジや鍋で中心まで熱を通す(75℃以上が目安)
- 生野菜や刺身など加熱できない食材は、その場で食べきるようにする
- 翌日までに食べ切ることを前提に、長期保存は避ける
安全に美味しく楽しむためにも、基本的な保存と加熱のルールを守ることが大切です。
特に小さなお子様や高齢者がいる家庭では、慎重な取り扱いが求められます。
自分の容器を持参する際のメリット
近年、環境配慮の意識の高まりとともに、自分専用の持ち帰り容器を持参する人が増えてきました。
タッパーウェアやステンレス容器、エコバッグなどを活用することで、以下のような多くの利点があります:
- 一度きりの使い捨て容器を減らし、ごみを削減できる
- 繰り返し使えるため、長期的に見ると経済的にもお得
- 自分好みのサイズや形状を選べるので、使い勝手が良い
- 密閉性や保温性に優れた容器を使えば、持ち帰り後も安心
ただし、店舗によっては衛生上の理由から持参容器の使用を断られることもあります。
事前にスタッフへ相談し、対応可能かを確認することが必要です。
また、持参する容器は清潔であることが前提となります。
食べ残しの持ち帰りは、私たち一人ひとりがすぐにできる食品ロス対策のひとつです。
ガストのような身近な飲食店で、持ち帰りの仕組みを上手に活用すれば、無理なく環境にやさしい行動ができます。
毎日の外食に、ちょっとした「もったいない」精神をプラスして、地球にも財布にもやさしい食生活を実現していきましょう。
ガスト以外のファミレスの持ち帰り事情
バーミヤンの持ち帰り方法
バーミヤンでは、店舗内での飲食に加え、テイクアウトメニューが非常に充実しています。専用のアプリやウェブサイトから注文できる利便性に加えて、事前決済が可能なため、店舗での待ち時間を大幅に短縮できます。
人気メニューのチャーハンや餃子、油淋鶏(ユーリンチー)なども持ち帰りができ、自宅で手軽に本格中華料理を味わえる点が、多くのユーザーに支持されています。さらに、定期的に行われるキャンペーンや割引サービスを活用すれば、コストパフォーマンスも抜群です。
また、バーミヤンのテイクアウト容器は、料理の温かさや食感を保つ設計がなされており、持ち帰っても店内と変わらぬクオリティを楽しむことができます。地域によっては、配達サービスとの連携も進んでおり、忙しい家庭や共働き世帯にとっては心強い味方となっています。
ステーキガストの特徴
ステーキガストでは、ステーキやハンバーグといった肉料理を中心に、ボリューム満点のメニューを持ち帰ることができます。
特に、ライスやサラダがセットになった定食スタイルのメニューは、栄養バランスも良く、満足度の高い食事として人気があります。
食べ残しをそのまま廃棄せずに、自宅で再び楽しむための工夫がしやすいのも魅力です。
テイクアウト用の容器は、耐熱性や密閉性に優れており、汁漏れの心配もほとんどありません。安心して持ち帰ることができ、家族や友人とシェアすることも可能です。
さらに、アレルギー情報や栄養成分の表示も明確にされており、健康志向の人にも配慮されたサービスが提供されています。
ファミレス全体での廃棄物削減への取り組み
近年、ファミレス業界全体で食品ロスの削減が重要な社会的課題として認識されつつあります。
多くの企業が、持ち帰り容器の導入、食べ残しの持ち帰りを推奨するポスター掲示、スタッフによる声かけなどを通じて、意識改革を進めています。
また、メニューの適正量化やオプション選択制の導入によって、注文時から無駄を省く取り組みも増加傾向にあります。
さらに、一部の店舗では、未使用の食材や調理過程で出たロスを堆肥や飼料として再利用するなど、環境に配慮したサステナブルな活動を進めています。地域社会との連携により、余剰食材を福祉施設へ提供する取り組みも始まっており、業界全体の意識が大きく変化しています。
持ち帰りによって得られる体験
自宅での再利用アイデア
持ち帰った料理は、そのまま食べるだけでなく、少しのアレンジを加えることで全く新しい料理に生まれ変わります。
たとえば、バーミヤンの餃子はスープに加えて水餃子風に、チャーハンは卵や野菜を追加して焼き飯風にリメイク、ステーキガストのハンバーグはカレーにトッピングしたり、パンにはさんでハンバーガーにするなど、楽しみ方はさまざまです。
また、子どもと一緒に調理することで、食育の一環としても活用できます。
料理の変化を楽しむことは、家庭内のコミュニケーションを深める良い機会にもなり、食材を無駄にしない意識も自然と身につきます。
持ち帰った料理の美味しい保存法
料理の種類に応じた適切な保存方法が重要です。
冷蔵保存では、密閉容器に入れて翌日でも美味しく食べられます。数日保存する場合は冷凍保存がおすすめで、ライス系は小分けしてラップに包み冷凍、食べる際には電子レンジでふっくらと加熱します。
油分や水分が多い料理は、ラップで包みジッパーバッグに入れることで、風味を損なわずに保存できます。解凍の際は、自然解凍後に電子レンジやフライパンで加熱することで、できたてに近い味わいが楽しめます。保存前には日付の記入を忘れずに行いましょう。
食品ロス削減へのサポートとしての意義
食べ残しを持ち帰る行動は、小さなエコアクションです。
一人ひとりの行動が、社会全体の食品ロス削減や持続可能な社会の実現に寄与します。
また、子どもたちにとっては、食べ物を大切にする姿勢や環境問題への関心を育む貴重な機会にもなります。
まとめ

持ち帰り文化の広がりと未来
ファミレス各社の取り組みや利用者の意識の変化により、持ち帰り文化はライフスタイルの一部に定着しつつあります。
今後の展望としては、環境に優しい容器の開発、レシピ付きメニューの拡充、地域連携によるフードシェアリングなど、多様な展開が期待されます。
持ち帰りを「食事の延長体験」として捉えることで、より豊かでサステナブルな暮らしが実現できるでしょう。
あなたの食べ残しを救うアクション
今日の一食が、明日の未来を変える一歩になります。
ちょっとした工夫で料理が再び輝き、持ち帰りという選択が、あなた自身の食生活を豊かにし、社会全体の食品ロス削減にも大きな影響を与えることになります。
あなたの行動が、未来を変える力になります。