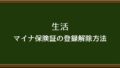「学級閉鎖」と「学年閉鎖」という言葉は似ていますが、実際には異なる意味を持っています。
今回は、この2つの違いをわかりやすく説明し、それぞれが実施される際の基準についてもお伝えします。
学級閉鎖と学年閉鎖の違いとは?
どちらもインフルエンザやノロウイルス、コロナウイルスなど、感染力の強い病気の流行を抑えるための措置です。
「学級閉鎖」は、特定のクラスだけを閉鎖して休みにする対応です。一方、「学年閉鎖」は、その規模をさらに広げ、同じ学年全体を対象とした措置になります。
例えば、学級閉鎖の場合は2年A組だけが休みとなり、他の2年B組や2年C組は通常通り授業を行います。しかし、学年閉鎖となると、2年生全体が休みとなり、全クラスが一定期間、自宅で学習することになります。
つまり、学級閉鎖は一部のクラスのみの対応であるのに対し、学年閉鎖ではその学年全体が対象になる点が大きな違いです。
判断基準はあるの?
学級閉鎖や学年閉鎖について、法律上は具体的な基準が定められていません。
たとえば、「何人以上が欠席したら閉鎖する」「欠席率が何%を超えたら閉鎖する」といった全国共通のルールは存在しません。そのため、各学校が状況を見て判断する形になります。
ただし、学校によっては独自の基準を設けている場合もあります。一般的には、感染症の流行状況や欠席者数を考慮しながら、学校が適切な対応を決定します。
法律では、「学校設置者は感染症予防のために必要と判断した場合、学校の一部または全部を休業することができる」と規定されています。そのため、最終的な判断は学校側に委ねられています。
具体的には、特定のクラスで感染者が集中している場合には学級閉鎖を行い、学年全体に感染が広がり、多くのクラスで欠席者が出ている場合には学年閉鎖を行う、といった対応が一般的です。
このように、学級閉鎖や学年閉鎖には全国共通の明確な基準はなく、それぞれの学校がその時の状況を考慮しながら判断する仕組みになっています。
閉鎖対象になった場合の過ごし方
もし自分のクラスや学年が閉鎖の対象になった場合、その期間中は自宅で過ごすことになります。基本的には自宅学習という形になりますが、実際はほとんどお休みに近い感覚です。
過ごし方については、クラス閉鎖でも学年閉鎖でも特に変わりません。ある程度自由に過ごして問題ありませんが、外で堂々と遊んでいると先生と偶然会って注意される可能性や、「平日に遊んでいるのはおかしい」と近所の人に思われることも考えられます。そのため、必要な外出以外は家でゆっくり過ごすのがおすすめです。
また、自分自身は健康でも、インフルエンザなどの感染症は潜伏期間があります。そのため、後から体調を崩す可能性もゼロではありません。特に旅行など長距離移動を伴う行動は避けた方が安心です。
閉鎖範囲が広がる可能性
最初は特定のクラスのみが閉鎖されていても、感染が広がれば学年全体が閉鎖されることもあり得ます。
こうした判断は学校側が行いますが、閉鎖されたクラスの生徒と接点を持つ人はどのクラスにもいるため、感染を防ぐための基本的な対策が欠かせません。普段以上に手洗いやうがいを徹底し、クラス全体で注意することが大切です。
まとめ
学級閉鎖と学年閉鎖の違いは、閉鎖される範囲にあります。学級閉鎖は特定のクラスを対象とし、学年閉鎖は学年全体が対象です。
どちらの場合も、学校内で感染症が広がっている状況には変わりありません。そのため、自分のクラスが閉鎖対象でない場合でも、油断せず基本的な予防策(手洗いやうがいなど)を徹底しましょう。
過度に不安になる必要はありませんが、気を抜くこともリスクにつながります。常に適切な行動を心がけてください。