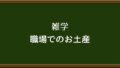日本各地には、団子にまつわるさまざまな伝統が受け継がれています。
例えば、十五夜に月を眺めながら楽しむ「お月見団子」、桜の季節に味わう「お花見団子」、お盆にお供えする「迎え団子」や「送り団子」など、季節ごとに特別な団子があります。
その中でも、あまり知られていない「十六団子」という風習には、どのような意味があるのでしょうか?
また、この伝統を大切にしている地域はどこなのでしょうか?
今回は、十六団子の起源や、その風習を大切に守り続ける地域の文化について詳しくご紹介します。
十六団子の由来と意味
「十六団子」(じゅうろくだんご)は、その名の通り、16個の団子を供える伝統的な風習です。
日本では古くから、山には神が宿るという信仰がありました。3月16日は農作業の始まりを告げる日とされ、この日には農業の神が山から田へ降りてくると考えられています。そして、収穫を終えた11月16日(地域によっては10月16日)には、神が再び山へ戻ると信じられています。
この信仰は「神去来(かみきょらい)」と呼ばれ、神を迎えたり送り出したりする大切な行事です。杵と臼を使って餅をつき、神への感謝と豊作を祈願する風習があり、餅をつく音が神への合図になるともいわれています。
このような風習から、餅を16個の団子にして神に供える「十六団子」が生まれました。3月16日は「十六団子の日」として知られ、農業に関わる重要な神事として今日まで受け継がれています。
ただし、この風習がいつ頃始まったのかについては、明確な記録は残されていません。
十六団子の由来:なぜ16日に16個の団子を供えるのか?
十六団子の風習は、なぜ16という数や日付が選ばれたのでしょうか?
この風習の背景には、「嘉祥の日」と呼ばれる歴史的な出来事が関係しています。
平安時代中期、疫病が流行した際に、仁明天皇は元号を「承和」から「嘉祥」に改めました。当時、天災や疫病が発生すると元号を変更するのが一般的でしたが、一世一代の元号制度が確立されたのは明治時代以降のことです。
嘉祥元年(848年)、仁明天皇は神のお告げを受け、「6月16日に16個のお菓子を神前に供えるように」と命じました。この儀式により、16個のお菓子を捧げたところ、疫病が鎮まったと伝えられています。
この出来事がきっかけとなり、6月16日は「嘉祥の日」として定められ、江戸時代まで「嘉祥菓子」を食べる習慣が続きました。
この歴史にちなんで、「十六団子」は農作業の節目である3月16日(農耕開始)と11月16日(収穫終了)に、16個の団子を神前に供える風習として広まりました。この伝統は、農業の節目を祝うだけでなく、厄除けや健康祈願の意味も込められ、現代に受け継がれています。
「十六団子」が親しまれている地域
「十六団子」という伝統的な風習は、岩手県や青森県を中心に、東北地方や北陸地方の一部で広く受け継がれています。
地域や家庭ごとに、団子の数や作り方、味付けにそれぞれの工夫が加えられ、独自のスタイルが根付いています。
近年では、杵と臼を使って餅をつく機会が減り、代わりに米粉や上新粉を使って手軽に作る方法が主流になっています。こうした団子は、今でも神様へのお供えとして大切にされています。
昔はお供えした団子をそのまま食べることが一般的でしたが、現在ではきな粉やあずきをまぶしたり、みたらし団子にしたり、お汁粉に入れるなど、さまざまな楽しみ方が広がっています。また、団子の数にこだわらず、農作業の始まりや田植えの時期に食べるなど、地域に根付いた習慣も見られます。
この行事は年に2回、特定の日に行われることが多く、かつては餅をついて神様に一年の節目を報告する習わしがありました。現在では餅つきをする機会は減ったものの、家族や友人と一緒に十六団子を楽しむことで、伝統を身近に感じることができます。
まとめ
日本各地に根付く団子文化の中でも、「十六団子」は特別な意味を持つ存在です。その歴史や地域ごとの特色についてご紹介します。
十六団子の起源と意味
日本では、昔から山に神が宿ると信じられており、農耕の神が春に山から田へ降り、秋に再び山へ戻ると考えられてきました。この信仰に基づき、春の訪れを祝う3月16日と収穫への感謝を示す11月16日に、団子をお供えする「神去来」という風習が生まれました。
16個の由来
平安時代の中頃、疫病の流行を鎮めるために元号を「嘉祥」に改めた際、天皇が神のお告げを受け、6月16日に16個の菓子を奉納する儀式を行いました。この習慣が広まり、農耕に関連する行事でも16個の団子を供えるようになったとされています。
地域ごとの特徴
東北地方の岩手県や青森県、北陸地方などでは特に盛んに行われており、地域や家庭ごとに団子の材料や味付けが異なります。一般的に、米粉や上新粉が使われることが多いです。
多彩な食べ方
かつては供えた団子をそのまま食べることが一般的でしたが、現在ではきな粉をまぶしたり、みたらし団子にするなど、さまざまな楽しみ方が広がっています。
十六団子の風習は、古くからの信仰と現代の生活が調和した、日本独自の文化として受け継がれています。